1. はじめに:時代ごとの“あるある”とは?
「あるあるネタ」とは、誰もが経験したり目にしたりしたことのある出来事を、ユーモラスに共感を誘う形で表現する文化です。日常の一コマや世代ごとの価値観、流行、習慣などが元ネタになることが多く、時代によってその“あるある”も大きく変化してきました。
本記事では、昭和・平成・令和という3つの時代をテーマに、それぞれの“あるある”をAIが分析・創作しながら紹介していきます。
「懐かしい!」「わかる~!」といった共感から、「今こんな感じなの!?」という発見まで、読みながら時代の流れを楽しんでいただければ幸いです。
人気記事トップ5
2. 昭和あるある編|モノクロテレビとちゃぶ台と
昭和(1926〜1989)は戦後の高度経済成長期からバブル崩壊前までの激動の時代。人々の暮らしには今では見られないアナログな習慣や、人情味のある光景があふれていました。そんな昭和の“あるある”を、AI視点でユーモラスに10個ご紹介します。

昭和あるある①:チャンネルは「ガチャガチャ」回すダイヤル式
今や当たり前となったリモコンですが、昭和中期までの家庭用テレビにはそんな便利なものは存在しませんでした。番組を変えるときは、わざわざ立ち上がってテレビの前まで行き、「ガチャガチャッ」とダイヤルを回す必要がありました。
この「ガチャガチャ」という音と手応えは、多くの昭和世代にとっては耳に焼き付いた記憶。勢いよく回しすぎると、隣のチャンネルを飛び越してしまったり、「あれ?戻しすぎた!」とまた回し直したり──それもまた日常の一部でした。
家庭では、子どもが“チャンネル係”として任命されることもしばしば。特にちゃぶ台を囲んでの食事中、父親や祖父が「3チャンに変えてくれ」と指示を出すと、子どもがテレビの前にダッシュしてガチャっと切り替える──そんな光景が全国の茶の間にあふれていました。
しかも、当時のテレビはブラウン管でサイズも重く、ダイヤル部分が固くなっていたり調子が悪くなると、うまく回らなかったり、映像がノイズだらけになったりすることも。そんなときは決まって「叩けば直る!」という謎のメンテナンス技が発動し、テレビの横を“ポンッ”と軽く叩くのもお約束。これはもはや昭和の都市伝説のひとつとも言えるでしょう。
また、チャンネル数も限られており、東京でも6〜7局程度、地方では3局以下という地域も珍しくありませんでした。だからこそ、番組の選択肢が少ないぶん、家族で観るものを決める“家庭内民主主義”が発動し、番組内容で口論が始まるなんてことも。
テレビを変えるというシンプルな行動に、ここまでの“儀式”と“人間ドラマ”があったのは、まさに昭和ならではの風景です。
昭和あるある②:夏のクーラーは「冷えピタ」と団扇
昭和の夏といえば、“暑さとの根性勝負”。現在のようにどこにでも冷房がある時代ではなく、家庭用エアコンは高価で「ぜいたく品」扱いでした。多くの家庭ではまだ設置されておらず、**「自然風+手動の工夫」**で乗り切るのが当たり前。
窓は全開、カーテンはなびき、扇風機が「ウィ〜ン…」と低音を響かせながら首を振る。冷蔵庫から出した氷をタオルでくるんで首に巻いたり、おばあちゃんが持っていた竹の団扇であおいでもらったり…。氷水で濡らした手ぬぐいをおでこに乗せるだけでも、ほんのひとときの“極楽”。
そして、昭和の子どもたちの夏といえば「扇風機に向かって喋る」遊びが定番。
「あ〜〜〜〜」と声を出せば、機械の風で声が震え、まるでロボットのような響きになる。それを聞いて兄弟姉妹で大笑い──エアコンがなくても、そこにはしっかり“夏の記憶”が刻まれていました。
また、夜は氷枕を用意して就寝。保冷剤などない時代、ビニール袋に入れた氷水をタオルで包み、頭元に置いて眠りにつく家庭も多かったのです。
現代では“熱中症対策”が重要視されていますが、昭和では「水を飲みすぎるとバテる」と信じられていた時代背景もあり、今では考えられない我慢の美学が日常に溶け込んでいました。
昭和あるある③:ちゃぶ台を囲んで家族団らん
ちゃぶ台は、昭和の家庭における**「暮らしの中心」**でした。テーブルのように椅子で囲むのではなく、座布団に正座して向き合う形で、家族が自然と一つの空間に集まりました。
このちゃぶ台のまわりでは、ご飯・会話・叱責・笑い・涙…すべてが生まれていたと言っても過言ではありません。
父親が仕事から帰ってくると、みんながそろって「いただきます」。母親が味噌汁をよそい、兄がテレビの音量を上げ、妹が箸を忘れて怒られる──そんな日常のドラマが、毎晩繰り広げられていたのです。
中でも象徴的なのが、「ちゃぶ台返し」。ドラマや漫画の影響で有名になったこの行動、実際に目にした人は少ないかもしれませんが、“ちゃぶ台の存在感”がいかに大きかったかを物語るエピソードです。
また、ちゃぶ台は“折りたたみ式”が多く、食事が終われば片付けて部屋を広く使うという合理性もありました。畳の部屋に一台。シンプルで無駄のない日本的暮らしの象徴でもありました。
テレビ番組も、お茶も、おやつも、全部がちゃぶ台に集まり、家族の気配がそこにあった。
今のように「自室で個食」ではなく、「みんなで同じ時間を共有する」ことが、自然に行われていた時代──それが昭和のちゃぶ台文化なのです。
昭和あるある④:電話は黒電話、しかも家に1台だけ
スマホどころか、コードレス電話もなかった昭和の家庭にとって、「黒電話」は通信の要。
家の中で1台きり、たいていは居間か玄関の近くに置かれており、家族全員が共用するのが当たり前でした。
特徴的なのは、今では見かけなくなった**「ダイヤル式」**。
0〜9までの数字の穴に指を入れ、「じ〜こじ〜こ…カチン」と回して番号を入力。電話番号の最後が「0」だと、ダイヤルを大きく回さなければならず、もどかしい思いをした人も多いはずです。
通話時はプライバシーゼロ。
家族全員がそばにいる中での通話になるため、好きな人からの電話には緊張が走りました。
「誰から?」「何の用?」とすぐに詮索され、ヒソヒソ話すと「聞こえないよ!」と親に怒られる…。電話1本が家庭のちょっとしたドラマになる時代でした。
しかも、電話線の長さ=行動範囲。
「せめて玄関までコード伸ばして!」と引っ張って、ドアの隙間から顔を出しながら話すスタイルも。
今の感覚で言えば、「LINEのやり取りを家族全員が見ている」ようなもの。
それでも、あの“じ〜こじ〜こ”のリズムと音には、どこか温もりがありました。
昭和あるある⑤:「ジャンケンで負けた人が買いに行く」が万能ルール
昭和キッズにとって、「ジャンケン」はまさに生活のルールメーカー。
兄弟で何かを決める時、友達とどちらがやるか決める時──全てはジャンケンで解決!
「最初はグー、じゃんけんぽん!」の声が響けば、そこには公平と運命が共存していました。
アイスを買いに行く係、お風呂を最初に沸かす係、テレビのチャンネルを変える係…。
すべてが「ジャンケンで負けた人」の役目。
文句を言う者は許されず、ジャンケンに負けた=納得すべしという不文律が存在しました。
中には、「あいこでしょ!」が10回以上続いて爆笑が起きる場面も。
ジャンケンそのものが遊びやコミュニケーションの一部だったのです。
現代のように「アプリで順番を管理」するような便利なものはなく、
“人と人との勝負”が、日常の小さな意思決定を支えていた昭和時代。
シンプルなのに、みんなが納得する──
ジャンケンには**「民主主義」の原型**があったのかもしれません。
昭和あるある⑥:学校の掃除は「ぞうきんがけダッシュ」
昭和の学校では、清掃も教育の一環。
現在のようなモップや掃除ロボットは存在せず、“ぞうきん”が清掃の主力兵器でした。
特に印象的なのが、廊下での「ぞうきんがけダッシュ」。
雑巾を床に押し付け、両手で這いつくばりながら走るように進む姿は、まるでスポーツ。
いつの間にか友だちと競争になり、「どっちが早く端まで行けるか!」というバトルに発展しがちでした。
もちろん、先生に見つかれば「廊下で走るな!」と怒られるのがオチ。
それでも、教室に戻る頃には額に汗がにじみ、どこか達成感すら感じるのが“ぞうきんがけ”の魅力。
ぞうきんも、買ったものではなく家から持参するボロ布の再利用。
母親が古くなったタオルを切って作ってくれたものや、家の雑巾をそのまま持ってくる生徒も多く、家庭の気配が学校に滲み出ていた時代でした。
掃除の時間は面倒だけど、みんなで一緒にやることで、自然と協力心や責任感が育つ──。
まさに“昭和の教育”が詰まった光景です。
昭和あるある⑦:放課後は「秘密基地」づくりに夢中
インターネットもスマホもなかった昭和時代。
子どもたちにとって、冒険と創造の舞台は「空き地」「裏山」「神社の裏」など、近所のちょっとした場所でした。
段ボール、ベニヤ板、竹、ブルーシートなど、拾ってきた材料で**“秘密基地”を組み立てるのが放課後の日課**。
「ここがリーダー席」「ここに宝物を隠そう」「入り口にはトラップを!」など、
まるで建築家のようにワクワクしながら作り上げていくプロセスが、何よりの遊びでした。
もちろん、親には「行っちゃダメ」と言われる場所も多く、その“禁止されてる感”もまた冒険心をくすぐるスパイス。
「今日は見張り役ね」「敵が来た!」など、役割分担や設定を作ってごっこ遊びも白熱しました。
今でいう「メタバース」や「サンドボックスゲーム」の原点かもしれません。
リアルな“空間の支配”と“仲間との共有”を楽しめる、まさに昭和ならではの贅沢な遊びでした。
昭和あるある⑧:「おばあちゃんの梅干し」はとにかく酸っぱい
スーパーで売っている甘い梅干しとは別物。
昭和のおばあちゃんが漬ける梅干しは、「酸っぱくて、しょっぱい」のが当たり前でした。
塩分20%以上、真っ赤なしその色、瓶の中にギュウギュウに詰められた梅たち…。
一粒食べるだけで、「うわっ酸っぱ!」と顔がくしゃくしゃになるほどの衝撃。
でも不思議とクセになり、おにぎりに入ってると最高にうれしかったりする。
「風邪をひいたら梅干しと番茶」「ご飯が進まないときは梅干しで一口」など、
“薬”としても“おかず”としても万能選手だった昭和の梅干し。
何より、「これね、おばあちゃんが漬けたのよ」という言葉に、
家庭の味とぬくもりが詰まっていたのです。
昭和あるある⑨:ビニールのカバー付きリモコンやソファ
昭和の家庭に一歩足を踏み入れると、目につくのは「何でもかんでもビニールカバー」文化。
テレビのリモコン、ソファ、電話機、扇風機のスイッチ…。
なぜか新品で買ったその日から、透明なビニールに包まれる運命。
「汚れないように」「長持ちさせるために」という理由でしたが、
使うたびにベタついたり、カバーが破れてテープで補修されていたり──その光景もまた“昭和感”の象徴です。
とくにソファは、ビニール越しに座ると「バリバリ」「ペリッ」と音が鳴る。
夏場は汗で張りついて、立ち上がるたびに不快音が…。でも、誰もカバーを外そうとはしませんでした。
昭和の美徳は「清潔感と節約」。
見た目よりも“物を大切に使う”という文化が、そこに表れていたのです。
昭和あるある⑩:「テレビの上に乗る猫」
ブラウン管テレビが当たり前だった時代。
テレビの上は平らで、しかも放熱でじんわり温かいという、猫にとって理想的なスポットでした。
どこの家でも「気づいたら猫がテレビの上に座っていた」なんてことが日常茶飯事。
「うちの子、チャンネルよりテレビの上が好きなのよ」なんて微笑ましい会話が交わされたものです。
でも問題なのが、猫の体が画面の一部を隠してしまうこと。
「ちょっと〜、画面見えないよ〜」「降りて!」と叫ぶと、猫がしぶしぶ伸びをしながらどく…そんな風景に、家族全員がなごんだ記憶も。
今や薄型テレビの普及で、猫が乗るスペースすらない時代になりましたが、
あの“猫 on テレビ”ののどかさは、まさに昭和の象徴。
人と動物が、アナログな機械と共に共存していた、温もりのある時間でした。
退職を伝えると「お前なんて他の会社じゃ使い物にならないし入社出来ない!」でもこういう人に限って
3. 平成あるある編|ガラケーとプリクラとファミレスの時代
昭和から続くアナログ文化に別れを告げ、テクノロジーと個人主義が加速した平成(1989〜2019)。
「ケータイ世代」や「ゆとり世代」など、多様な価値観が生まれたこの時代ならではの“あるある”を、AI目線でピックアップしました。

平成あるある①:メールは「絵文字」と「顔文字」で感情表現
平成初期〜中期は、スマホやSNSがまだ存在せず、**コミュニケーションの主役は“メール”**でした。
特にガラケー時代には、文章に彩りを添えるために「絵文字」や「顔文字」が大活躍。
「(^_^)」「(T_T)」「☆彡」「(≧∀≦)」など、気持ちや雰囲気を伝えるツールとして欠かせない存在で、
文章の最後に入れ忘れると「機嫌悪いの?」と誤解されるほど、感情表現の必須パーツでした。
また、当時は**デコメール(絵文字装飾付きのメール)**が流行し、フォントサイズや色、背景を変えて「私らしさ」を表現するのも定番。
中高生カップルの間では、1日数十通の長文メールをやり取りするのが日常で、告白や悩み相談もメールで完結することが多かったのです。
文章だけで心を伝える力が磨かれた時代とも言えます。
今ではスタンプや短文が主流になりましたが、「顔文字でしか伝えられない微妙なニュアンス」も、確かに存在していました。
平成あるある②:ガラケーの「着うたフル」を必死で探す
平成中期、音楽の楽しみ方が大きく変わったきっかけのひとつが「着うた」ブーム。
とくに**“着うたフル”は自分の個性をアピールする重要アイテム**でした。
お気に入りのアーティストのサビ部分を探し、ドコモ・au・ソフトバンク各社の音楽配信サイトを巡回。
「レコ直」「mu-mo」などの専用サイトからダウンロードするのが一般的でしたが、
一曲に数百円かかるため、お小遣いと相談しながら選ぶ慎重さもまた青春の一幕。
中には、**CDを借りてパソコンに取り込み、自作で編集→赤外線通信で友達に配る“着うた職人”**のような存在も。
「〇〇に着信があると〇〇の曲が鳴る」という演出が嬉しく、
恋人専用の着うたを設定してドキドキした人も多かったのではないでしょうか。
今でこそ通知音はミュートが当たり前になりましたが、当時は**“音で魅せる時代”**。
ガラケーの着信音こそ、平成の青春を彩るサウンドトラックだったのです。
平成あるある③:「プリクラ帳」は友情の証
「プリクラ撮りに行こうよ」は、平成を象徴する女子中高生の合言葉。
放課後の定番コースはゲーセン → プリクラブース。
天使の羽、ハートフレーム、落書き機能、目が大きくなる“美肌盛り”──
まるで魔法のような加工で“盛る”のが当然の文化でした。
撮ったプリクラは、ただの思い出では終わりません。
1枚ずつハサミで切り、「プリ帳(プリクラ帳)」に貼ってコレクション。
友達の名前や日付、エピソードなどを書き添えながら、自分だけの友情アルバムを完成させていくのです。
「新しい友達ができたらまずプリクラ撮る」
「卒業間近は連日撮りまくり」
“友情の証=プリクラ”という価値観が強く、多くの女子が肌身離さずプリ帳を持ち歩いていました。
スマホで写真をシェアする時代とは違い、「手で持ち、目で見る」アナログな絆のかたちが、そこにはありました。
平成あるある④:ファミレスが社交場だった
「放課後どこ行く?」「とりあえずサイゼじゃね?」──
このやりとりこそ、平成の若者文化の象徴でした。
ジョナサン、デニーズ、ガスト、サイゼリヤなど、ファミレスは**学生から社会人まで誰でも受け入れる“憩いの場”**として人気を博しました。
特に高校生・大学生の間では、数百円で無限に粘れる“ドリンクバー”が聖域。
“アイスティー+メロンソーダのミックス”など、独自のブレンドを作って盛り上がる遊びもありました。
課題の相談、恋バナ、バンドメンバーの打ち合わせ、バイト先の愚痴大会…
ありとあらゆる青春の語らいがファミレスで繰り広げられていたのです。
3時間以上居座っても咎められないという自由さと、
財布にやさしいメニューの数々は、まさに**「平成のユースカルチャーの母」**とも言える存在でした。
今のようにカフェでノマド…という時代ではなく、「仲間とだらだら過ごす」ことそのものが贅沢だった時代──それが平成だったのです。
平成あるある⑤:「mixi」の足あとが恋のバロメーター
SNSがまだ浸透していなかった時代、「mixi(ミクシィ)」はインターネットの出会いと交流の最前線でした。
特徴的だったのが「足あと機能」。
誰が自分のプロフィールを見に来たかがわかる仕様で、特定の人の足あとが毎日付いていると──
「これ、脈アリかも…?」
足あと=恋のサインという方程式が成立していたのです。
当時はコメントやメッセージを送るにも慎重で、
「何文字で送れば好印象か」「コメント欄に残すか、メッセージにするか」などを深夜まで悩む青春が、そこにはありました。
さらに「マイミク申請」も一大イベント。
相互フォローにならないとプロフィールの詳細が見られない設計のため、
「マイミク=認め合った関係」という重みもありました。
今のSNSでは忘れられがちな**“つながりの距離感”を丁寧に測る時代**──
mixiはまさにデジタル恋愛初期の象徴的ツールでした。
平成あるある⑥:赤外線通信で連絡先交換
今やLINEやAirDropで一瞬の情報共有が当たり前になりましたが、
平成のケータイ時代は**「赤外線通信」こそが最先端の連絡手段**でした。
「アドレス教えて〜」のひと言で始まる連絡先交換。
お互いの携帯電話をピタッと近づけ、端末の赤外線ポート同士を合わせる儀式が始まります。
ところがこの通信、思ったより不安定でシビア。
「読み取れない」「データが壊れた」「角度が合ってない」など、
何度もケータイの位置を微調整しながらやっとの思いで成功させる、**“通じ合うための儀式”**でもありました。
教室や駅のホームで立ったままケータイを突き合わせる光景は、
平成の若者文化を象徴する日常のひとコマ。
今振り返れば不便かもしれませんが、
そのひと手間こそが「特別なやりとり」を演出していたのかもしれません。
平成あるある⑦:テレビ番組は「録画」して繰り返し見る
平成の家庭に欠かせなかったのが、VHSビデオデッキ。
お気に入りのドラマやアニメを**“録画予約”して保存し、何度も繰り返し観る文化**が当たり前でした。
録画した番組はCM部分を手動で早送りしながら観るのが定番。
ビデオテープの残り時間を気にしながら、上書きミスにヒヤッとすることも多々。
間違えて大事な番組の上に父親のゴルフ番組が録画されていて、家族内で小さな悲劇が起きることもしばしばありました。
テープが絡んで“ガチャガチャガチャ…”という音とともにデッキに巻き込まれた日には、絶望感MAX。
あの独特のビデオ臭、手作業で巻き戻すカチャカチャ音も含めて、平成の家庭のぬくもりでした。
今のようにサブスクやYouTubeが主流になる前、「好きな番組を録っておく」こと自体が愛情表現だったのです。
平成あるある⑧:「ルーズソックス」はJKの正装
1990年代後半〜2000年代初頭の女子高生ファッションといえば、
「ルーズソックス」なくして語れません。
制服のスカートに合わせて履く、膝下でクシャっとたるんだ白い靴下。
中には“ルーズソックス専用の糊”でずり落ちないように固定する人も。
当時は「くるぶしソックス=子どもっぽい」「普通のソックス=ダサい」といった空気があり、
ルーズソックスこそが“おしゃれJK”の証しだったのです。
雑誌『egg』や『Popteen』で紹介されるギャルモデルはこぞってルーズスタイル。
渋谷のセンター街でたむろする“コギャル文化”の象徴としても語り継がれています。
いまでは懐かしいアイテムとなったルーズソックスですが、
**「あの頃のJKは最強に可愛かった」**と語る世代も少なくありません。
平成あるある⑨:カラオケで「アニメ主題歌」全力熱唱
カラオケとアニソン──
この組み合わせが青春のすべてだった人、少なくないはずです。
90年代〜2000年代前半にかけて、『新世紀エヴァンゲリオン』『るろうに剣心』『ドラゴンボールZ』などのアニメ主題歌が社会現象に。
『残酷な天使のテーゼ』『魂のルフラン』『そばかす』『CHA-LA HEAD-CHA-LA』などは、
「カラオケで誰かが必ず歌う曲」ランキング上位の常連でした。
歌詞を覚えていないのに勢いでマイクを握りしめ、サビだけ熱唱するのも“あるある”。
サークルの飲み会、友達同士の遊び、好きな人にアピールしたい夜──
カラオケは、「音楽+感情+勇気」が交錯する場だったのです。
平成のアニソンは“オタク”の領域を超え、
誰もが知っているポップカルチャーとして市民権を得た瞬間でした。
平成あるある⑩:卒業アルバムの「黒歴史率」が高すぎる
誰もが笑って振り返れる…はずがない、それが卒アル。
前髪パッツン、超盛りのギャルメイク、意味不明なヤンキー座り。
なぜあのタイミングで、あの髪型を選んだのか──
未来の自分にツッコミを入れたくなるような写真が並ぶのは、平成世代の宿命です。
「全力で青春を生きていた証拠」とは言いつつも、
再会した同級生と卒アルを開いた瞬間に
**「ちょっ…見ないで!」「やば、黒歴史www」**と盛り上がるのも、また一興。
なぜか全体的に表情が硬い、服のセンスが壊滅的、背景の色が謎。
昭和ほど堅くなく、令和ほど映えも狙っていない、
「ちょうどいいダサさ」が残るのが平成の卒アルなのです。
ChatGPTに変な質問をしてみたら想像以上に面白すぎた【AIとの不思議な対話集】
4. 令和あるある編|Z世代とAIとマスクの時代
令和(2019年〜)は、コロナ禍・リモート文化・AI・Z世代といった新しいキーワードが次々と登場し、価値観や行動様式が一変した時代です。
デジタルネイティブ世代を中心に広がった“今っぽいあるある”を、AI目線でユーモラスに10個紹介します。

令和あるある①:「とりあえずChatGPTに聞く」──新世代の相談相手?
かつては「ググれ」が当たり前だった検索文化。
しかし令和の若者たちは違います。彼らはまずスマホを開いて──ChatGPTに聞く。
調べもの、レポートの下書き、英作文、さらにはLINEの返信文すら、
「ちょっとAIに聞いてみよ」が自然な選択肢になっています。
特にZ世代にとっては、検索エンジンよりも**“相談相手”に近い感覚**。
「何が正しいか」よりも「どんな可能性があるか」を求めてAIと会話するのです。
Google検索が“答えを探すツール”なら、ChatGPTは**“問いを深める対話のパートナー”**。
知識を得るだけでなく、自分の考えを整理する手段としても活用され始めています。
ただし、リテラシーの差も明確に出る時代。
「全部AI任せ」にするのか、「活用するツール」として使いこなすかで、
情報格差や表現力の差もますます広がっています。
令和あるある②:「バズる」か「映える」かが行動基準
「どこ行く?」「何食べる?」の判断基準が、
「映えるか」「バズりそうか」で決まるのが令和の感性。
現地の味や雰囲気よりも、
**「TikTokで紹介されてた!」「インスタで見て気になってた」**が動機になる。
行ってみたら混んでて写真だけ撮って帰る、なんてのも“あるある”。
SNSに載せるための**“映える角度”や“加工フィルター”を前提に行動する**のも当たり前で、
カフェも観光地も「#映えスポット」として評価される時代です。
その一方で、「リアルよりデジタル上での価値」の優先という逆転現象も起きています。
“実体験”より“共感と拡散”が重視されることで、
日常生活がどんどんSNSネイティブ化しているのが、令和の特徴です。
令和あるある③:マスクしてる顔のほうが見慣れてる
コロナ禍を経験したZ世代にとって、
“顔”の定義はマスクありきになりました。
「マスクをしている姿のほうが可愛い/カッコいい」と思う人も多く、
マスクを外す瞬間に「誰?」となることも。
「マスク美人」「マスク詐欺」などの新語が生まれ、
マスクが“第二の化粧”として使われる時代になっています。
また、「素顔を見せる=気を許した証」的な感覚もあり、
恋愛や人間関係の“距離感”を測る新たなツールにもなっています。
いまやマスクは、単なる感染予防の道具ではなく、
自己演出・心理的な防御・美意識の一部として生活に定着しています。
令和あるある④:「Z世代」って呼ばれたくないZ世代
「Z世代」──メディアが好んで使うこの言葉に、
当の本人たちはモヤモヤした反応を示します。
「また勝手にラベリングしてる」「自分たちはそんなに一括りじゃない」
そんな声がSNSで目立ち、**“カテゴライズ疲れ”**の空気が漂っています。
彼らにとって、「○○世代だからこう」という断定はむしろダサい。
むしろ、**「私は私。個で見てほしい」**という個人主義が強い傾向にあります。
それは、SNS時代に自分らしさや多様性が重視されてきた影響でもあります。
「Z世代あるある」自体が、**Z世代的には“ないあるある”**なのかもしれません。
令和あるある⑤:YouTubeよりTikTokのほうが“検索エンジン”
「気になることはまずYouTubeで検索」
──そんな時代は、もはや少し前の話。
今や多くのZ世代は、「GoogleよりTikTokでタグ検索」が当たり前。
飲食店、メイク、旅行スポット、商品レビュー……
すべてを“短尺動画”でサクッと確認するのが現代流です。
特に「実際に使ってみた」「行ってみた」などの体験型コンテンツは、
テキスト情報より“信頼できる”と感じる傾向が強く、
文字より映像、映像より“人の感情”が重視されるようになっています。
また、AIやアルゴリズムの力で関連情報が次々出てくるため、
「検索する」より「発見される」感覚で情報と出会う人も増えています。
TikTokはもはやSNSではなく“感覚検索エンジン”。
次世代のGoogleとも言える存在になりつつあります。
令和あるある⑥:スニーカーは“コレクション”の時代へ
「スニーカーは履いてナンボ」だったのは、もう昔。
令和では、履かずに“飾る”スニーカーが主流になりつつあります。
ナイキやアディダスの限定モデルはもちろん、
トラヴィス・スコットやシュプリームとのコラボ商品など、
希少性=ステータスという文化が加速。
中には“履く用”と“保管用”で同じ靴を2足購入するコレクターも珍しくありません。
箱(BOX)ごと大切に保存し、スニーカー専用の収納ケースや
ディスプレイ棚で**“魅せるコレクション”**として扱う人も。
さらに注目すべきは、リセール(再販)市場の拡大。
「将来的に高く売れる」という投資的な目線でスニーカーを買う若者も増えており、
スニーカーは今や**“趣味”と“資産”を兼ね備えたカルチャー**になっています。
令和あるある⑦:「動画はYouTubeよりもTikTokで見る」
令和の若者にとって、「動画=YouTube」の時代はすでに過去。
今は、縦型・短尺・エンタメ性の三拍子が揃ったTikTokがスタンダードです。
「10分の解説動画を見ていられない」
「ニュースも要点だけでいい」
そんなニーズにピタリとハマるのが、TikTokのショート動画文化。
さらに、スクロールで次々と動画が流れてくる“沼設計”により、
**「気づけば1時間見ていた」**という現象も日常茶飯事。
令和世代にとってTikTokは単なる娯楽ではなく、
ニュース、メイク、勉強、恋愛術、投資などあらゆる情報のハブとして活用されています。
今後も、動画視聴の主導権はTikTokが握り続けると見られ、
YouTubeが“長尺専門”にシフトするのも時間の問題かもしれません。
令和あるある⑧:「推し活」が日常に浸透。沼が深い。
「推しは推せるうちに推せ」
──この言葉が、Z世代の新しい人生訓として浸透しています。
“推し活”とは、好きなアイドル・声優・俳優・Vtuber・アニメキャラなどを応援する活動全般のこと。
ジャンルや形式にとらわれず、誰もが推しを持ち、日常の一部として楽しむのが令和流。
推しの出演番組を見る
推しカラーのネイルを塗る
推しをテーマにしたカフェに通う
推しグッズの写真をSNSにアップする
など、表現の仕方は人それぞれ。
また、「沼」や「供給」など独自の用語も広まり、推し活はひとつのカルチャーとして成熟。
かつてはオタク的とされていた文化が、いまや**“誰もが自然に楽しむライフスタイル”**へと変貌を遂げています。
令和あるある⑨:「マッチングアプリで出会うのが普通」
「出会いはアプリでした」──この一言が珍しくなくなった時代。
むしろ「使ってないの?」と驚かれることもあるほど、マッチングアプリは令和恋愛のインフラになっています。
Pairs(婚活志向)
Tinder(カジュアル)
タップル(20代中心)
with(性格診断系)
Omiai(真面目な交際向け)
など、用途や年代、目的によって使い分けが進化。
プロフィール文を工夫したり、写真の撮り方を研究したり、まるで自己ブランディングのように活用する人も。
「アプリでの出会い」はもはや特別なものではなく日常の一部であり、
結婚式で「出会いはマッチングアプリ」と紹介されても驚かれない時代です。
令和あるある⑩:「何でも“AIでやってみた”がバズる」
SNSや動画コンテンツでは、「AIに○○させてみた」系の投稿が大人気。
AIで作詞した歌を歌ってみた
AIに理想の彼氏を描かせてみた
ChatGPTに恋愛相談してみた
AIに昭和のアイドル風写真を作らせてみた
などなど、“AIを使った遊び”がコンテンツとして成り立つ時代です。
特にZ世代は、新しい技術に対するハードルが低く、
「ツール=おもちゃ」「試すこと=遊び」として受け止める傾向が強め。
AIが生成した画像や文章に個性や表現を重ねる“共創型”コンテンツは、
今後ますます伸びていくジャンルとなるでしょう。
5.おわりに:時代が変われば“あるある”も変わる
“昭和のぬくもり、平成の多様化、そして令和のデジタル文化。
それぞれの時代の“あるある”には、その時代を生きた人たちのリアルな生活、価値観、笑いと共感が詰まっています。
「懐かしい!」と思わず声に出した人、
「それ、今でもやってるかも…」と感じた人、
「そんな時代があったの!?」と驚いた人──
世代を超えて“あるある”を共有することは、
人と人との心の距離を縮め、時代を超えた対話を生むきっかけになるはずです。
未来のあるあるは、どんな風になっていくのでしょうか?
それもまた、時代が教えてくれることでしょう。
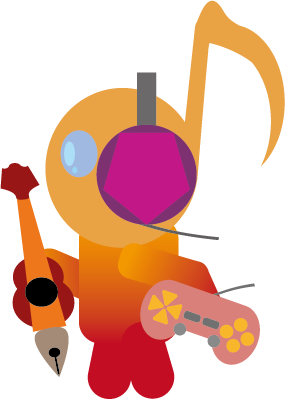








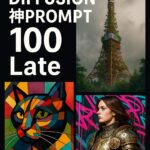

コメント